
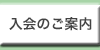
Home > 島根県社会福祉士会 概要 > 倫理綱領など
| 島根県社会福祉士会 概要 |
| 会長から皆様へ 社会福祉士 新着情報 倫理綱領など 入会案内 リンク集 掲示板 お問い合わせ |
1.社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領改訂への経過
○ 社団法人日本社会福祉士会は、1999年6月1日の第4回通常総会で倫理委員会の設置を採
択した。倫理委員会の任務は、「1)倫理綱領の改訂、2)行動規範の策定、3)苦情処理」とされた。
これらの任務のうち、3)については「会員への苦情等に対応するシステム」として2001年6
月から稼動させている。
○ 倫理委員会の任務のうち、1)と2)に対しては、以下のような経過をたどり、社団法人日本社会
福祉士会の改定案を提起するに至った。
1999.07.17 第1回日本社会福祉士会倫理委員会の開催
2000.12.19 日本ソーシャルワーカー協会と日本社会福祉士会とで、倫理綱領改訂のための合
同作業委員会を立ち上げるための協議
2001.03.17 日本医療社会事業協会も参画し、3団体で倫理綱領改訂のための作業を開始
2002.10.17 「ソーシャルワーカーの倫理綱領改訂案」を公表し、3団体合同作業委員会が、
パブリックコメントを求める
2002.12.28 「ソーシャルワーカーの倫理綱領改訂案」をさらに修正していくこと並びに日本
精神保健福祉士協会が参画し、4団体合同の委員会を立ち上げることを決定
2003.01.18 4団体の方向性を確認し、「改訂案」を一部修正した「改訂試案」を倫理委員会
が日本社会福祉士会役員会にて報告
2003.07 「『ソーシャルワーカーの倫理綱領』改訂試案詳細解説」を倫理委員会が全会員
に配布
2004.06.03 第9回通常総会で「社会福祉士の行動規範(案)」を公表し、倫理委員会が会員
に意見を求める。
2004.06.30 「ソーシャルワーカーの倫理綱領(改訂最終案)」を公表し、社会福祉専門職団
体協議会・倫理綱領委員会が、パブリックコメントを求める
2004.10.05 社会福祉専門職団体協議会・倫理綱領委員会が、日本における取り組みを国際ソ
ーシャルワーカー連盟主催の国際会議に発表
2005.01.27 「ソーシャルワーカーの倫理綱領(最終案)」と事業報告をとりまとめ、社会福
祉専門職団体協議会・倫理綱領委員会の解散を確認
2005.02.05 「社会福祉士の倫理綱領(案)」並びに「社会福祉士の行動規範(案)」を倫理
委員会において確認
2005.02.19 「社団法人日本社会福祉士の倫理綱領(案)」を、日本社会福祉士常任理事会・
理事会・代議員会において確認
2.社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領
○ 1995年1月20日に本会の倫理綱額として採択した「ソーシャルワーカーの倫理綱領」を
改訂し、2005年6月3日に開催した第10回通常総会にて採択するものである。
3.社会福祉士の倫理綱領
○ 前文
われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等で
あることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利
用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービ
ス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する。
われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすこと
に着目する時、この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠の制度であることを自覚すると
ともに、専門職社会福祉士の職責についての一般社会及び市民の理解を深め、その啓発に努める。
われわれは、われわれの加盟する国際ソーシャルワーカー連盟が採択した、次の「ソーシャル
ワークの定義」(2000年7月)を、ソーシャルワーク実践に適用され得るものとして認識し、
その実践の拠り所とする。
ソーシャルワークの定義
ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウエルビーイング)の増進を目指して、社会の変革
を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。ソー
シャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互
に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤
である。(IFSW;2000.07)
われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責で
あるだけでなく、サービス利用者は勿論、社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、
本綱領を制定してこれを遵守することを誓約する者により、専門職団体を組織する。
○ 価値と原則
1.(人間の尊厳)社会福祉士は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状
況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない
存在として尊重する。
2.(社会正義)社会福祉士は、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、
平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。
3.(貢献)社会福祉士は、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。
4.(誠実)社会福祉士は、本倫理綱領に対して常に誠実である。
5.(専門的力量)社会福祉士は、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。
○ 倫理基準
1.利用者に対する倫理責任
1-01.(利用者との関係) 社会福祉士は、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それ
を自己の利益のために利用しない。
1-02.(利用者の利益の最優先) 社会福祉士は、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優
先に考える。
1-03.(受容) 社会福祉士は、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるがままに受容する。
1-04.(説明責任) 社会福祉士は、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を
用いて提供し、利用者の意思を確認する。
1-05.(利用者の自己決定の尊重) 社会福祉士は、利用者の自己決定を尊重し、利用者がそ
の権利を十分に理解し、活用していけるように援助する。
1-06.(利用者の意思決定能力への対応) 社会福祉士は、意思決定能力の不十分な利用者に
対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。
1-07.(プライバシーの尊重) 社会福祉士は、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関
係者から情報を得る場合、その利用者から同意を得る。
1-08.(秘密の保持) 社会福祉士は、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範
囲にとどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。
1-09.(記録の開示) 社会福祉士は、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記
録を開示する。
1-10.(情報の共有) 社会福祉士は、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・
関係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。
1-11.(性的差別、虐待の禁止) 社会福祉士は、利用者に対して、性別、性的指向等の違い
から派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。
1-12.(権利侵害の防止) 社会福祉士は、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止
する。
2.実践現場における倫理責任
2-01.(最良の実践を行う責務) 社会福祉士は、実践現場において、最良の業務を遂行する
ために、自らの専門的知識・技術を惜しみなく発揮する。
2-02.(他の専門職等との連携・協働) 社会福祉士は、相互の専門性を尊重し、他の専門職
等と連携・協働する。
2-03.(実践現場と綱領の遵守) 社会福祉士は、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じ
るような場合、実践現場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働
きかける。
2-04.(業務改善の推進) 社会福祉士は、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進す
る。
3.社会に対する倫理責任
3-01.(ソーシャル・インクルージョン) 社会福祉士は、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、
排除、暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を目指すよう努める。
3-02.(社会への働きかけ) 社会福祉士は、社会に見られる不正義の改善と利用者の問題解
決のため、利用者や他の専門職等と連帯し、効果的な方法により社会に働きかける。
3-03.(国際社会への働きかけ) 社会福祉士は、人権と社会正義に関する国際的問題を解決
するため、全世界のソーシャルワーカーと連帯し、国際社会に働きかける。
4.専門職としての倫理責任
4-01.(専門職の啓発) 社会福祉士は、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を
伝え社会的信用を高める。
4-02.(信用失墜行為の禁止) 社会福祉士は、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。
4-03.(社会的信用の保持) 社会福祉士は、他の社会福祉士が専門職業の社会的信用を損な
うような場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。
4-04.(専門職の擁護) 社会福祉士は、不当な批判を受けることがあれば、専門職として連
帯し、その立場を擁護する。
4-05.(専門性の向上) 社会福祉士は、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・
研修に参加し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。
4-06.(教育・訓練・管理における責務) 社会福祉士は教育・訓練・管理に携わる場合、相
手の人権を尊重し、専門職としてのよりよい成長を促す。
4-07.(調査・研究) 社会福祉士は、すべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫
理性を確保する。
4.社会福祉士の行動規範
この「社会福祉士の行動規範」は、「社会福祉士の倫理綱領」に基づき、社会福祉士が社会福
祉実践において従うべき行動を示したものである。
1.利用者に対する倫理責任
1-01.利用者との関係
1-01-1.社会福祉士は、利用者との専門的援助関係についてあらかじめ利用者に説明しなけれ
ばならない。
1-01-2.社会福祉士は、利用者と私的な関係になってはならない。
1-01-3.社会福祉士は、いかなる理由があっても利用者およびその関係者との性的接触・行動
をしてはならない。
1-01-4.社会福祉士は、自分の個人的・宗教的・政治的理由のため、または個人の利益のため
に、不当に専門的援助関係を利用してはならない。
1-01-5.社会福祉士は、過去または現在の利用者に対して利益の相反する関係になることが避
けられないときは、利用者を守る手段を講じ、それを利用者に明らかにしなければなら
ない。
1-01-6.社会福祉士は、利用者との専門的援助関係とともにパートナーシップを尊重しなけれ
ばならない。
1-02.利用者の利益の最優先
1-02-1.社会福祉士は、専門職の立場を私的なことに使用してはならない。
1-02-2.社会福祉士は、利用者から専門職サービスの代償として、正規の報酬以外に物品や金
銭を受けとってはならない。
1-02-3.社会福祉士は、援助を継続できない何らかの理由がある場合、援助を継続できるよう
に最大限の努力をしなければならない。
1-03.受容
1-03-1.社会福祉士は、利用者に暖かい関心を寄せ、利用者の立場を認め、利用者の情緒の安
定を図らなければならない。
1-03-2.社会福祉士は、利用者を非難し、審判することがあってはならない。
1-03-3.社会福祉士は、利用者の意思表出をはげまし支えなければならない。
1-04.説明責任
1-04-1.社会福祉士は、利用者の側に立ったサービスを行う立場にあることを伝えなければな
らない。
1-04-2.社会福祉士は、専門職上の義務と利用者の権利を説明し明らかにした上で援助をしな
ければならない。
1-04-3.社会福祉士は、利用者が必要な情報を十分に理解し、納得していることを確認しなけ
ればならない。
1-05.利用者の自己決定の尊重
1-05-1.社会福祉士は、利用者が自分の目標を定めることを支援しなければならない。
1-05-2.社会福祉士は、利用者が選択の幅を広げるために、十分な情報を提供しなければなら
ない。
1-05-3.社会福祉士は、利用者の自己決定が重大な危険を伴う場合、あらかじめその行動を制
限することがあることを伝え、そのような制限をした場合には、その理由を説明しなけ
ればならない。
1-06.利用者の意思決定能力への対応
1-06-1.社会福祉士は、利用者の意思決定能力の状態に応じ、利用者のアドポカシーに努め、
エンパワメントを支援しなければならない。
1-06-2.社会福祉士は、自分の価値観や援助観を利用者に押しつけてはならない。
1-06-3.社会福祉士は、常に自らの業務がパターナリズムに陥らないように、自己の点検に務
めなければならない。
1-06-4.社会福祉士は、利用者のエンパワメントに必要な社会資源を適切に活用しなければな
らない。
1-07.プライバシーの尊重
1-07-1.社会福祉士は、利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければな
らない。
1-07-2.社会福祉士は、利用者の個人情報を収集する場合、その都度利用者の了解を得なけれ
ばならない。
1-07-3.社会福祉士は、問題解決を支援する目的であっても、利用者が了解しない場合は、個
人情報を使用してはならない。
1-08.秘密の保持
1-08-1.社会福祉士は、業務の遂行にあたり、必要以上の情報収集をしてはならない。
1-08-2.社会福祉士は、利用者の秘密に関して、敏感かつ慎重でなければならない。
1-08-3.社会福祉士は、業務を離れた日常生活においても、利用者の秘密を保持しなければな
らない。
1-08-4.社会福祉士は、記録の保持と廃棄について、利用者の秘密が漏れないように慎重に対
応しなければならない。
1-09.記録の開示
1-09-1.社会福祉士は、利用者の記録を開示する場合、かならず本人の了解を得なければなら
ない。
1-09-2.社会福祉士は、利用者の支援の目的のためにのみ、個人情報を使用しなければならな
い。
1-09-3.社会福祉士は、利用者が記録の閲覧を希望した場合、特別な理由なくそれを拒んでは
ならない。
1-10.情報の共有
1-10-1.社会福祉士は、利用者の情報を電子媒体等により取り扱う場合、厳重な管理体制と最
新のセキュリティに配慮しなければならない。
1-10-2.社会福祉士は、利用者の個人情報の乱用・紛失その他あらゆる危険に対し、安全保護
に関する措置を講じなければならない。
1-10-3.社会福祉士は、電子情報通信等に関する原則やリスクなどの最新情報について学ばな
ければならない。
1-11.性的差別、虐待の禁止
1-11-1.社会福祉士は、利用者に対して性的差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待を行っ
てはならない。
1-11-2.社会福祉士は、利用者に対して肉体的・精神的損害または苦痛を与えてはならない。
1-11-3.社会福祉士は、利用者が暴力や性的搾取・虐待の対象となっている場合、すみやかに
発見できるよう心掛けなければならない。
1-11-4.社会福祉士は、性的差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待に対する正しい知識を
得るよう学ばなければならない。
1-12.権利侵害の防止
1-12-1.社会福祉士は、利用者の権利について十分に認識し、敏感かつ積極的に対応しなけれ
ばならない。
1-12-2.社会福祉士は、利用者の権利侵害を防止する環境を整え、そのシステムの構築に努め
なければならない。
1-12-3.社会福祉士は、利用者の権利侵害の防止についての啓発活動を積極的に行わなければ
ならない。
2.実践現場における倫理責任
2-01.最良の業務遂行の責務
2-01-1.社会福祉士は、専門職としての使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を深め、
理論と実務に精通するように努めなければならない。
2-01-2.社会福祉士は、専門職としての自律性と責任性が完遂できるよう、自らの専門的力量
の向上をはからなければならない。
2-01-3.社会福祉士は、福祉を取り巻く分野の法律や制度等関連知識の集積に努め、その力量
を発揮しなければならない。
2-02.他の専門職等との連携.協働
2-02-1.社会福祉士は、所属する機関内部での意思疎通が円滑になされるように積極的に働き
かけなければならない。
2-02-2.社会福祉士は、他の専門職と連携し、所属する機関の機構やサービス提供の変更や開
発について提案しなければならない。
2-02-3.社会福祉士は、他機関の専門職と連携し協働するために、連絡・調整の役割を果たさ
なければならない。
2-03.実践現場と綱領の遵守
2-03-1.社会福祉士は、社会福祉士の倫理綱領を実践現場が熟知するように働きかけなければ
ならない。
2-03-2.社会福祉士は、実践現場で倫理上のジレンマが生じた場合、倫理綱領に照らして公正
性と一貫性をもってサービス提供を行うように努めなければならない。
2-03-3.社会福祉士は、実践現場の方針・規則・手続き等、倫理綱領に反する実践を許しては
ならない。
2-04.業務改善の推進
2-04-1.社会福祉士は、利用者の声に耳を傾け苦情の対応にあたり、業務の改善を通して再発
防止に努めなければならない。
2-04-2.社会福祉士は、実践現場が常に自己点検と評価を行い、他者からの評価を受けるよう
に働きかけなければならない。
3.社会に対する倫理責任
3-01.ソーシャル・インクルージョン
3-01-1.社会福祉士は、特に不利益な立場にあり、抑圧されている利用者が、選択と決定の機
会を行使できるように働きかけなければならない。
3-01-2.社会福祉士は、利用者や住民が社会の政策・触度の形成に参加することを積極的に支
援しなければならない。
3-01-3.社会福祉士は、専門的な視点と方法により、利用者のニーズを社会全体と地域社会に
伝達しなければならない。
3-02.社会への働きかけ
3-02-1.社会福祉士は、利用者が望む福祉サービスを適切に受けられるように権利を擁護し、
代弁活動を行わなければならない。
3-02-2.社会福祉士は、社会福祉実践に及ぼす社会政策や福祉計画の影響を認識し、地域福祉
の増進に積極的に参加しなければならない。
3-02-3.社会福祉士は、社会における意思決定に際して、利用者の意思と参加が促進されるよ
う支えなければならない。
3-02-4.社会福祉士は、公共の緊急事態に対して可能な限り専門職のサービスを提供できるよ
う、臨機応変な活動への貢献ができなければならない。
3-03.国際社会への働きかけ
3-03-1.社会福祉士は、国際社会において、文化的社会的差異を尊重しなければならない。
3-03-2.社会福祉士は、民族、人種、国籍、宗教、性別、障害等による差別と支配をなくすた
めの国際的な活動をささえなければならない。
3-03-3.社会福祉士は、国際社会情勢に関心をもち、精通するよう努めなければならない。
4.専門職としての倫理責任
4-01.専門職の啓発
4-01-1.社会福祉士は、対外的に社会福祉士であることを名乗り、専門職としての自覚を高め
なければならない。
4-01-2.社会福祉士は、自己が獲得し保持している専門的力量を利用者・市民・他の専門職に
知らせるように努めなければならない。
4-01-3.社会福祉士は、個人としてだけでなく専門職集団としても、責任ある行動をとり、そ
の専門職の啓発を高めなければならない。
4-02.信用失墜行為の禁止
4-02-1.社会福祉士は、社会福祉士としての自覚と誇りを持ち、社会的信用を高めるよう行動
しなければならない
4-02-2.社会福祉士は、あらゆる社会的不正行為に関わってはならない。
4-03.社会的信用の保持
4-03-1.社会福祉士は、専門職業の社会的信用をそこなうような行為があった場合、行為の内
容やその原因を明らかにし、その対策を講じるように努めなければならない。
4-03-2.社会福祉士は、.他の社会福祉士が非倫理的な行動をとった場合、必要に応じて関係
機関や日本社会福祉士会に対し適切な行動を取るよう働きかけなければならない。
4-03-3.社会福祉士は、信用失墜行為がないように互いに協力し、チェック機能を果たせるよ
う連携を進めなければならない。
4-04.専門職の擁護
4-04-1.社会福祉士は、社会福祉士に対する不当な批判や扱いに対し、その不当性を明らかに
し、社会にアピールするなど、仲間を支えなければならない。
4-04-2.社会福祉士は、不当な扱いや批判を受けている他の社会福祉士を発見したときは、一
致してその立場を擁護しなければならない。
4-04-3.社会福祉士は、社会福祉士として不当な批判や扱いを受けぬよう日頃から自律性と倫
理性を高めるために密に連携しなければならない。
4-05.専門性の向上
4-05-1.社会福祉士は、研修・情報交換・自主勉強会等の機会を活かして、常に自己研鋳に努
めなければならない。
4-05-2.社会福祉士は、常に自己の専門分野や関連する領域に関する情報を収集するよう努め
なければならない。
4-05-3.社会福祉士は、社会的に有用な情報を共有し合い、互いの専門性向上に努めなければ
ならない。
4-06.教育・訓練・管理における責務
4-06-1.スーパービジョンを担う社会福祉士は、その機能を積極的に活用し、公正で誠実な態
度で後進の育成に努め社会的要請に応えなければならない。
4-06-2.コンサルテーションを担う社会福祉士は、研修会や事例検討会等を企画し、効果的に
実施するように努めなければならない。
4-06-3.職場のマネジメントを担う社会福祉士は、サービスの質・利用者の満足・職員の働き
がいの向上に努めなければならない。
4-06-4.業務アセスメントや評価を担う社会福祉士は、明確な基準に基づき評価の判断をいつ
でも説明できるようにしなければならない。
4-06-5.社会福祉教育を担う社会福祉士は、次世代を担う人材養成のために、知識と情熱を惜
しみなく注がなければならない。
4-07.調査・研究
4-07-1.社会福祉士は、社会福祉に関する調査研究を行い、結果を公表する場合、その目的を
明らかにし、利用者等の不利益にならないよう最大限の配慮をしなければならない。
4-07-2.社会福祉士は、事例研究にケースを提供する場合、人物を特定できないように配慮し、
その関係者に対し事前に承認を得なければならない。
・1986年4月26日 日本ソーシャルワーカー協会の倫理綱領として宣言
・1992年4月25日 ソーシャルワーカーの倫理綱領とすることに決定
・1993年1月15日 日本社会福祉土会の倫理綱領として採択
・1995年1月20日 社団法人日本社会福祉土会の倫理綱領として採択
前文
われわれソーシャルワーカーは、平和擁護、個人の尊厳、民主主義という人類普遍の原理にのっとり、福祉専門職の知識、技術と価値観により、社会福祉の向上とクライエントの自己実現を目ざす専門職であることを言明する。
われわれは、社会の進歩発展による社会変動が、ともすれば人間の疎外(反福祉)をもたらすことに着目する時、この専門職が福 祉社会の維持、推進に不可欠の制度であることを自覚するとともに、専門職の職責について一般社会の理解を深め、その啓発に努める。
われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責であるだけでなく、クライエントは勿論、社会全体の利益に密接に関連していることに鑑み、本綱領を制定し、それに賛同する者によって専門職団体を組織する。
われわれは、福祉専門職としての行動について、クライエントは勿論、他の専門職あるいは一般社会に対しても本綱領を遵守することを誓約するが、もし、職務行為の倫理性について判断を必要とすることがある際には、行動の準則として本綱領を基準とすることを宣言する。
原則
1(人間としての平等と尊厳)
人は、出自、人種、国籍、性別、年齢、宗教、文化的背景、社会的経済的地位、あるいは社会に対する貢献度いかんにかかわらず、すべてかけがえのない存在として尊重されなければならない。
2(自己実現の権利と社会の責務)
人は、他人の権利を侵害しない限度において自己実現の権利を有する。
社会は、その形態の如何にかかわらず、その構成員の最大限の幸福と便益を提供しなければならない。
3(ワーカーの職責)
ソーシャルワーカーは、日本国憲法の精神にのっとり、個人の自己実現、家族、集団、地域社会の発展を目ざすものである。また、社会福祉の発展を阻害する社会的条件や困難を解決するため、その知識や技術を駆使する責務がある。
クライエントとの関係
1(クライエントの利益の優先)
ソーシャルワーカーは、職務の遂行に際して、クライエントに対するサービスを最優先に考え、自己の私的な利益のために利用することがあってはならない。また、専門職業上の知識や技術が、非人間的な目的に利用されないよう自戒する必要がある。
2(クライエントの個別性の尊重)
ソーシャルワーカーは、個人・家族・集団・地域社会の文化的差異や多様性を尊重するとともに、これら差異あるクライエントに対しても、同等の熱意をもってサービスや援助を提供しなければならない。
3(クライエントの受容)
ソーシャルワーカーは、クライエントをあるがままに受容し、たとえクライエントが他者の利益を侵害したり、危害を加える恐れのある場合であっても、未然に事故を防止し、決してクライエントを拒否するようなことがあってはならない。
4(クライエントの秘密保持)
ソーシャルワーカーは、クライエントや関係者から事情を聴取する場合も、業務遂行上必要な範囲にとどめ、プライバシー保護のためクライエントに関する情報を第三者に提供してはならない。もしその情報がクライエントや公共の利益のため必要な場合は、本人と識別できる方法を避け、できれば本人の承認を得なければならない。
機関との関係
1(所属機関と綱領の精神)
ソーシャルワーカーは、常に本倫理綱領の趣旨を尊重しその所属する機関、団体が常にその基本精神を遵守するよう留意しなければならない。
2(業務改革の責務)
ソーシャルワーカーは、所属機関、団体の業務や手続の改善、向上を常に心がけ、機関、団体の責任者に提言するようにし、仮りに通常の方法で改善できない場合は責任ある方法によってその趣旨を公表することができる。
3(専門職の声価の保持)
ソーシャルワーカーは、もし同僚がクライエントの利益を侵害したり、専門職業の声価を損なうようなことがある場合は、その事実を本人に指摘したり、それぞれの所属する専門職団体に対して必要な措置をとることを要求することができる。
行政・社会との関係
1(専門的知識・技術の向上)
ソーシャルワーカーは、常にクライエントと社会の新しいニーズを敏感に察知し、クライエントによるサービスの選択の範囲を広げるため自己の提供するサービスの限界を克服するようにし、クライエントと社会に対して貢献しなければならない。
2(専門的知識・技術の応用)
ソーシャルワーカーは、その業務遂行によって得た専門職業上の知識を、クライエントのみならず、一般市民の社会生活の向上に役立てるため、行政や政策、計画などに積極的に反映させるようにしなければならない。
専門職としての責務
1(専門職の維持向上)
ソーシャルワーカーは、同僚や他の専門職業家との知識経験の交流を通して、常に自己の専門的知識や技能の水準の維持向上につとめることによって、所属機関、団体のサービスの質を向上させ、この専門職業の社会的声価を高めなければならない。
2(職務内容の周知徹底)
ソーシャルワーカーは、社会福祉の向上を目ざす専門職の業務や内容を一般社会に周知させるよう努力しなければならない。この場合、公的な場での発言が個人としてものか、専門職としての立場によるものかを明確にする必要がある。
3(専門職の擁護)
ソーシャルワーカーは、実践を通して常にこの専門職業の知識、技術、価値観の明確化につとめる。仮にもこの専門職が不当な批判を受けることがあれば、専門職の立場を擁護しなければならない。
4(援助方法の改善向上)
ソーシャルワーカーは、同僚や他の専門職業家の貢献や業績を尊重し、自己や同僚の業績やサービスの効果、効率について常に検討し、援助方法の改善、向上に心がけなければならない。
5(同僚との相互批判)
ソーシャルワーカーは、同僚や他の専門職業家との間に職務遂行の方法に差異のあることを容認するとともに、もし相互批判の必要がある場合には、適切、妥当な方法、手段によらなければならない。
1986年4月26日宣言
前文
われわれソーシャルワーカーは、平和擁護、個人の尊厳、民主主義という人類普遍の原理にのっとり、福祉専門職の知識、技術と価値観により、社会福祉の向上とクライエントの自己実現を目ざす専門職であることを言明する。
われわれは、社会の進歩発展による社会変動が、ともすれば人間の疎外(反福祉)をもたらすことに着目する時、この専門職が福祉社会の維持、推進に不可欠の制度であることを自覚するとともに、専門職の職責について一般社会の理解を深め、その啓発につとめる。
われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責であるだけでなく、クライエントは勿論、社会全体の利益に密接に関連していること に鑑み、本綱領を制定し、それに賛同する者によって専門職団体を組織する。
われわれは、福祉専門職としての行動について、クライエントは勿論、他の専門職或いは一般社会に対しても本綱領を遵守することを誓約するが、もし、職務行為の倫理性について判断を必要とすることがある際には、行動の準則として本綱領を基準とすることを宣言する。
原則
1.(人間としての平等と尊厳)
人は、出自、人権、国籍、性別、年齢、宗教、文化的背景、社会経済的地位、あるいは社会に対する貢献度いかんにかかわらず、すべてかけがえのない存在とし尊重されなけれぱならない。
2.(自己実現の権利と社会の責務)
人は、他の権利を侵害しない限度において自己実現の権利を有する。社会は、その形態の如何にかかわらず、その構成員の最大限の幸福と便益を提供しな ければならない。
3.(ワーカーの職責)
ソーシャルワーカーは、日本国憲法の精神にのっとり、個人の自己実現、家族、集団、地域社会の発展を目ざすものである。
また、社会福祉の発展を阻害する社会的条件や困難を解決するため、その知識や技術を駆使する責務がある。
クライエントとの関係
1.(クライエントの利益の優先)
ソーンャルワーカーは、職務の遂行に際して、クライエントに対するサービスを最優先に考え、自己の私的な利益のために利用することがあってはならない。また、専門職業上の知識や技術が、非人間的な目的に利用されないよう自戒する必要がある。
2.(クライエントの個別性の尊重)
ソーシャルワーカーは、個人・家族・集団・地域・社会の文化的差異や多様性を尊重するとともに、これら差異あるクライエントに対しても、同等の熱意をもってサ一ビスや援助を提供しなければならない。
3.(クライエントの受容)
ソーシャルワーカーは、クライエントをあるがままに受容し、たとえクライエントが他者の利益を侵害したり、危害を加える恐れのある場命であっても、未然に事故を防止し、決してクライエントを拒否するようなことがあってはならない。
4.(クライエントの秘密保持)
ソーシャルワーカーは、クライエントや関係者から事情を聴取する場合も、業務遂行上必要な範囲にとどめ、プライバシー保護のためクライエントに関する情報を第三者に提供してはならない。もしその情報提供がクライエントや公共の利益のために必要な場合は、本人と識別できる方法を避け、できれば本人の承詔を得なければならない。
機関との関係
1.(所属機関との綱領の精神)
ソーシャルワーカーは、常に本倫理綱領の趣旨を尊重し、その所属する機関、団体が常にその基本精神を遵守するよう留意しなければならない。
2.(業務改革の責務)
ソーシャルワーカーは、所属機関、団体の業務や手続きの改善、向上を常に心がけ機関、団体の責任者に提言するようにし、仮に通常の方法で改善でさない場合は責任ある方法によって、その趣旨を公表することができる。
3.(専門職業の声価の保持)
ソーシャルワーカーは、もし同僚がクライエントの利益を侵害したり、専門職業の声価を損なうようなことがある場合は、その事実を本人に指摘したり、本協会に対し規約第7条に規定する借置をとることを要求することができる。
行政・社会との関係
1.(専門的知識・技術の向上)
ソーシャルワーカーは、常にクライエントと社会の新しいニ一ズを敏感に察知し、クライエントによるサービス選択の範囲を広げるため自己の提供するサービスの限界を克服するようにし、クライエントと社会に対して貢献しなければならない。
2.(専門的知識・技術の応用)
ソーシャルワーカーは、その業務遂行によって得た専門職業上の知識を、クライエントのみならず、一般市民の社会生活の向上に役立てるため、行政や政策、計画などに積極的に反映させるようにしなければならない。
2000年7月27日モントリオールにおける総会において採択、日本語訳は日本ソーシャルワーカー協会、日本社会福祉士会、日本医療社会事業協会で構成するIFSW日本国調整団体が2001年1月26日決定した定訳である。
定義※
ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。
解説
様ざまな形態をもって行われるソーシャルワークは、人びととその環境の間の多様で複雑な相互作用に働きかける。その使命は、すべての人びとが、彼らのもつ可能性を十分に発展させ、その生活を豊かなものにし、かつ、機能不全を防ぐことができるようにすることである。専門職としてのソーシャルワークが焦点を置くのは、問題解決と変革である。
従ってこの意味で、ソーシャルワーカーは、社会においての、かつ、ソーシャルワーカーが支援する個人、家族、コミュニティの人びとの生活にとっての、変革をもたらす仲介者である。ソーシャルワークは、価値、理論、および実践が相互に関連しあうシステムである。
価値
ソーシャルワークは、人道主義と民主主義の理想から生まれ育ってきたのであって、その職業上の価値は、すべての人間が平等であること、価値ある存在であること、そして、尊厳を有していることを認めて、これを尊重することに基盤を置いている。ソーシャルワーク実践は、1世紀余り前のその起源以来、人間のニーズを充足し、人間の潜在能力を開発することに焦点を置いてきた。人権と社会正義は、ソーシャルワークの活動に対し、これを動機づけ、正当化する根拠を与える。ソーシャルワーク専門職は、不利益を被っている人びとと連帯して、貧困を軽減することに努め、また、傷つきやすく抑圧されている人びとを解放して社会的包含(ソーシャル・インクルージョン)を促進するよう努力する。ソーシャルワークの諸価値は、この専門職の、各国別並びに国際的な倫理綱領として具体的に表現されている。
理論
ソーシャルワークは、ソーシャルワークの文脈でとらえて意味のある、地方の土着の知識を含む、調査研究と実践評価から導かれた実証に基づく知識体系に、その方法論の基礎を置く。ソーシャルワークは、人間と環境の間の相互作用の複雑さを認識しており、また、人びとの能力は、その相互作用が人びとに働きかける様ざまな力〜それには、生体・心理社会的要因が含まれる〜によって影響を受けながらも、同時にその力を変えることができることを認識している。ソーシャルワーク専門職は、複雑な状況を分析し、かつ、個人、組織、社会、さらに文化の変革を促すために、人間の発達と行動、および社会システムに関する理論を活用する。
実践
ソーシャルワークは、社会に存在する障壁、不平等および不公正に働きかけて取り組む。そして、日常の個人的問題や社会的問題だけでなく、危機と緊急事態にも対応する。ソーシャルワークは、人と環境についての全体論的なとらえ方に焦点を合わせた様ざまな技能、技術、および活動を利用する。ソーシャルワークによる介入の範囲は、主として個人に焦点を置いた心理社会的プロセスから社会政策、社会計画および社会開発への参画にまで及ぶ。この中には、人びとがコミュニティの中でサービスや社会資源を利用できるように援助する努力だけでなく、カウンセリング、臨床ソーシャルワーク、グループワーク、社会教育ワークおよび家族への援助や家族療法までも含まれる。ソーシャルワークの介入には、さらに、施設機関の運営、コミュニティ・オーガニゼーション、社会政策および経済開発に影響を及ぼす社会的・政治的活動に携わることも含まれる。ソーシャルワークのこの全体論的な視点は、普遍的なものであるが、ソーシャルワーク実践での優先順位は、文化的、歴史的、および社会経済的条件の違いにより、国や時代によって異なってくるであろう。
※(注)ソーシャルワーク専門職のこの国際的な定義は、1982年に採択されたIFSW定義に代わるものである。21世紀のソーシャルワークは、動的で発展的であり、従って、どんな定義によっても、余すところなくすべてを言いつくすことはできないといってよいであろう。
2001年6月、第9回日本社会福祉士会全国大会において、「社会福祉士である自分たちの責務をもう一度問い直そう」という趣旨の大会宣言がなされました。
この全国大会の1ヶ月前に、和歌山県で介護支援専門員による殺人事件が発生していたことから、大会宣言を具体化する取り組みの1つとして、本会は「私たちのやくそく」を作成し、2002年5月31日に開催した本会第7回通常総会において報告しました。
本会会員の社会福祉士は「ソーシャルワーカーの倫理綱領」を遵守して行動し、権利擁護を推進する社会福祉専門職として、さまざまな場所で利用者と接しています。
「私たちのやくそく」は、介護支援専門員の業務に携わる会員の社会福祉士に対して、その責任と役割を自覚し、利用者に誠実に援助を提供していくことの重要性を再確認していこうと呼びかけるものです。
私たちのやくそく〜信頼される介護支援専門員になるために〜
1 私たちは、利用者の自立生活の実現を支援します。
介護支援専門員は、利用者の「自立支援」を目標として、介護サービスなどの調整や社会資源の活用をすすめたり、他の法律や制度に基づくサービスを紹介・あっせんしたりすることが役割です。
2 私たちは、利用者の自己決定を尊重し、その実現を支援します。
利用者の「自己決定」は、すべての基本です。自己決定したことをどのように実現するか、実現が困難であれば何が原因なのか、問題なのかを明らかにすることは介護支援専門員の役割です。
3 私たちは、利用者の自己決定に必要な情報を誠意をもって提供します。
利用者が自己決定するためには、適切な情報が必要です。利用者自身に関すること、社会資源に関することなど、利用者が現状で利用者なりに判断をすることができるようにすることは権利擁護の基本です。
4 私たちは、利用者の声を謙虚に受けとめ、敬意をもって尊重します。
利用者の疑問、不安、不満、苦情などは、利用者が自立して安心できる生活を営むことを損なう原因の一つです。それらに一つ一つ的確に応えていくことは、介護支援専門員がサービス提供する上で必要なことだけでなく、利用者の基本的な権利を守ることにもつながります。
5 私たちは、利用者の納得と承諾を得てサービスの提供と調整をします。
生活するのは利用者自身であり、いくらよいと思われるサービスを提供しても、利用者が納得できなければ、望ましい自立生活を営むことはできません。利用者が自ら利用するサービスを理解し、承諾することは、主体的に日常生活を営む上で欠かすことのできない権利です。
6 私たちは、利用者の生活支援に必要な権利擁護の制度を活用します。
利用者の心身の状況などにより、自ら情報を判断することや判断したことを表明することが困難な場合、利用者自身の権利を行使することが困難な場合には、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業など日常生活に必要な権利擁護の制度を活用して、利用者の生活を支援します。
7 私たちは、つねに自己点検し、自らのサービス評価をすすめます
介護支援専門員は、それぞれが基礎資格とする専門職としての倫理綱領などをもっています。専門職は、利用者や第三者からの評価だけでなく、つねに自己点検をし、自己評価をすることによって、専門職としての倫理を守っています。もちろん、他者からの評価については謙虚に受けとめることを忘れてはなりません。
8 私たちは、つねに自己研鑽に励み、介護支援サービスの向上をめざします。
自己評価や他者からの評価により、自分がその役割を果たす上で必要な知識や技能を確認し、その修得を図っていくことは重要なことです。資質向上を目指す自己研鑽は、自らが満足するだけでなく、利用者によりよいサービスを提供することや、利用者自身が自らの生活を豊かにしていく基礎となります。
9 私たちは、つねに公正な介護支援サービスと介護サービスを求めます。
介護支援専門員は、利用者の自立支援と自己決定をすすめていく役割をもっています。利用者にとって必要なサービスを調整するうえで重要なことは、サービス事業者の利害や関係者の利害からつねに公正な立場を保つことです。それが、利用者の権利を守る基本でもあります。
10 私たちは、介護支援サービスをとおして、利用者の権利擁護につくします。
利用者の権利擁護をすすめる取り組みは、さまざまです。介護支援専門員は、介護支援サービスという業務をとおして、利用者が自立した日常生活を営むことができるように直接的に支援するだけでなく、利用者が安心して暮らすことのできる社会を築く役割をもっています。利用者の権利擁護はさまざまな取り組みによって支えられるのです。介護支援サービスは、権利擁護をすすめるさまざまな活動の一つとして位置づけられるのです。